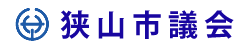
令和7年3月 定例会(第1回)
令和7年3月7日 (一般質問)
内藤光雄 (新政みらい)
録画を再生
1.令和6・7年度「市長施政方針」について
2.第2次狭山市自殺対策計画について
1.令和6・7年度「市長施政方針」について
(1)テーマ1「若い世代を増やす」について
a.若い世代の転入促進と転出抑制の両面を狙いとする、親元同居・近居支援補助制度及び若い世代の住宅取得支援補助制度の実績及び制度継続の見解は。
b.保育所と児童館との複合施設である、いりそ次世代支援センター「アイパレット」の利用状況と今後の展望は。
c.保育所及び学童保育室の新規開設状況と今後の待機児童解消の見込みは。
d.教頭のマネジメント業務を支援する人員の配置状況及び学校運営の機能強化に向けた進捗状況は。
e.モデル事業として進める民間スイミングスクールを活用した水泳指導の実施状況及び今後の展望は。
(2)テーマ2「まちと産業に活力を」について
a.カーボンニュートラルに向け「狭山サステナビリティ・トランスフォーメーション(略称SSX)」として取り組む各種セミナーの開催状況や温室効果ガス排出量の可視化などの進捗状況は。
b.カーボンニュートラルの目標時期となる2050年に対する進捗状況は。
c.上下水道事業において民間のノウハウを活用した包括的民間業務委託の推進状況及び具体的な委託内容は。
d.水道事業において人工衛星を活用した漏水調査の実施状況及び効果は。
e.人工衛星を活用した漏水調査を下水道事業に活用(反映)することは可能か。
(3)テーマ3「楽しめる健康高齢社会を」について
a.孤独死等を未然に防ぐ対策として進めるICTを活用した見守り体制の進捗状況及び効果は。
b.帯状疱疹のワクチン接種費用の一部助成事業の利用状況及び利用者の反応は。
c.公民館のトイレの洋式化の進捗状況及び今後の計画は。
(4)テーマ4「市政運営をみんなの力で」について
a.市民の負担を軽減することや利便性の向上のために取り組む「書かない窓口」及び「行かない窓口」の進捗状況は。また、利用者の反応及び今後の展望は。
b.自主財源の確保に向けて取り組む、ふるさと納税の返礼品の拡大状況及び企業版ふるさと納税の現状は。
c.犯罪発生の抑止や子どもたちの見守りも兼ねることができる街頭防犯カメラの設置状況及び効果は。
2.第2次狭山市自殺対策計画について
(1)自殺に関する現状と課題について
a.直近5年間の全国及び狭山市の自殺者数の推移と傾向は。
b.直近5年間の狭山市の自殺者の年代及び原因・動機は。
c.自殺対策を図る上での課題の分析状況は。
(2)児童・生徒に対する取り組みについて
a.小・中学校の教職員等で児童・生徒の悩みを的確に聴き取れる人材の育成状況とその効果は。
b.いのちを尊重する授業として中学生を対象に取り組む「いのちの授業」の実施状況と生徒の受け止めは。
c.児童・生徒の“SOS”を的確に受け止めるための方策と支援の状況は。
―――質問と答弁の要旨―――
◆狭山市への転入者の状況は?
Q1 若い世代の転入促進と転出抑制の両面を狙いとする、親元同居・近居支援補助制度及び若い世代の住宅取得支援補助制度の実績は?
A1 「親元同居・近居支援補助制度」は、制度を開始した平成29年度からの累積で450件、1億7,255万6千円であり、市外からの転入者数は1,386人となっている。次に「若い世代の住宅取得支援制度」は、制度を開始した令和2年度からの累積で979件、1億6,750万円であり、市外からの転入者数は1,299人、市内の転居者数は1,775人となっている。
◆保育所の拡大状況と待機児童解消の見込みは?
Q2 保育所及び学童保育室の新規開設状況は?
A2 保育所は令和6年4月に定員90 人の認可保育所を入曽地区に新たに開設したが、令和7年度に新規開設の予定はない。学童保育室は令和6年度に新狭山地区に定員40人の民間学童保育室を開室し、令和7年度も入間川地区に定員50人の民間学童保育室を開室する予定である。
Q3 今後の待機児童解消の見込みは?
A3 保育所は、既存の教育・保育施設内の定員調整や空き教室の活用及び、保育コンシェルジュによる入所希望先のマッチングを行うとともに、地域型保育事業所の整備等で待機児童の解消に至ると見込んでいる。学童保育室は、学校の余裕教室の活用や民間学童保育室の誘致なども含め、待機児童の解消に向けて努めていく。
◆狭山市の自殺者の状況は?
Q4 直近5年間の狭山市の自殺者数とその年代及び原因・動機は?
A4 本市の自殺者数は、R元年が28人、R2年が25人、R3年が21人、R4年が33人、R5年が32人となっており、男性は50歳代が19人で最も多く、次いで70歳代が14人となっており、女性は70歳代が11人で最も多く、次いで20歳代が9人となっている。また原因・動機については、健康問題が最も多く、次いで経済・生活問題、家庭問題となっている。
◆悩みを抱える児童・生徒への支援の状況は?
Q5 児童・生徒の“SOS”を的確に受け止めるための方策と支援の状況は?
A5 学期に1 回程度、学校生活の不安や悩みに関わるアンケートを学校独自に行うなど、児童生徒の心の変化や実態の把握に努めている。加えて今年度は年度当初に学校から児童生徒に対しSOSの出し方等に関する教育を年度内で実施するよう通知しており、道徳科の授業や学級指導の時間、全校朝会や学年集会などで学習している。