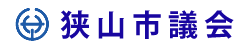
令和7年3月 定例会(第1回)
令和7年3月11日 (一般質問)
衣川千代子 (日本共産党)
録画を再生
1.障害者福祉
2.バリアフリーのまちづくり
1.障害者福祉
(1)高次脳機能障害
a.高次脳機能障害の講演会が5回目となるがどのように評価しているか。
b.市として家族教室や相談会などの次に繋がる対策の考えは。
c.埼玉県「高次脳機能障害者地域相談支援(サポート)事業」の活用の考えは。
d.ジョブコーチの現状と高次脳機能障害への対応は。
e.親亡き後の子の対策についての考えは。
2.バリアフリーのまちづくり
(1)民間事業者の合理的配慮
a.民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されたが市としての周知の考えは。
b.バリアフリー改修工事を実施する事業者への助成の考えは。
(2)入曽駅周辺整備におけるバリアフリー
a.入曽駅周辺整備におけるバリアフリーの状況は。
b.障害者団体との連携は。
c.バリアフリーの観点から見て東西自由通路の勾配4%をどう捉えているか。
(3)公共施設のバリアフリー化
a.公共施設のバリアフリーの現状は。
b.公共施設の建替や改修等は、障害者団体等の声を聞いて実施してほしいが考えは。
―――質問と答弁の要旨―――
◆高次脳機能障害講演会について
Q1 高次脳機能障害家族の会さやまがこれまで4回の講演会を実施しているが、市の評価は。
A1 講演会は、見た目からは分かりにくい高次脳機能障害の症状やリハビリなどについて、当事者や家族をはじめ、多くの市民が理解を深めるための重要な機会であると認識している。
◆講演会の後に繋がる対策の考えは
Q2 さいたま市は、ご家族向けに「家族教室」を、東京都港区は、当事者、家族、支援者のために「相談会」を開催しているが、市としての対策は。
A2 講演会の開催のみならず、次のステップとして、家族教室や相談会等についても、他市の事例を研究し、開催を検討していく。
◆親亡き後の子の対策は
Q3 市が実施したアンケート調査では、「将来的に生活する住まい、施設があるかどうか不安」との回答が全体の4分の1いることが分かった。市として親亡き後の子の対策の考えは。
A3 日頃から親亡き後の生活について考えておくことが重要であり、支援者などと将来の不安や対策などを話すことができる関係を構築しておくことが大切である。親亡き後の生活の場所として、グループホームなどの整備を推進することも重要な施策である。
◆バリアフリーのまちづくり
Q4 民間事業者の合理的配慮が義務化されたが、市としての周知の考えは。
A4 国による事業者向け説明会の周知やパンフレットを配布するなどの取組や狭山市障害者団体連絡会と連携し、民間事業者にも参考となる内容の勉強会を実施したところであり、今後も継続的に合理的配慮の理解促進を図っていく。
◆公共施設のバリアフリー化
Q5 公共施設である公民館の障害者用トイレが、男子トイレの奧にあり使いにくく、奥行きが狭いためドアが閉まらないという声がある。男子トイレを通らないようにするとか仕切る工夫はできないか。
A5 現在計画的に実施しております公民館トイレのリニューアル工事に併せて、より利用しやすいものとなるよう検討していく。