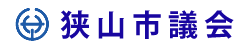
令和7年3月 定例会(第1回)
令和7年3月11日 (一般質問)
関根弘樹 (公明党)
録画を再生
1.公共交通
1.公共交通
(1)ほりかねデマンドバス
a.実証運行期間2年4か月を終えての実績は。
(a)登録人数と利用人数の推移と年代別
(b)1か月あたりの利用延べ人数と実人数
(c)収支状況
b.見えてきた利用傾向は。
(a)利用の多い時間帯や曜日の傾向
(b)乗降場所の傾向
c.主な改善の取り組みとその結果は。
d.実証運行のここまでの総括は。
(2)狭山市地域公共交通計画(案)の計画目標1「持続可能な地域公共交通を構築し、地域の環境にも配慮」について
a.「持続可能な地域公共交通の構築」とあるが、ここでの「持続可能」とは何を意味するのか。
b.公共交通の利用者増をはかるための「モビリティティマネジメント」とは、具体的にはどのようなことを想定しているか。
c.路線バスにおいて基幹路線以外は、減便や運行エリアの縮小も想定されるか。
d.「公共交通に関する情報提供、タイアップ企画」とは具体的にはどのようなものを想定しているか。
(3)狭山市地域公共交通計画(案)の計画目標2「誰もが安全・安心・快適に利用できる公共交通サービスの提供」について
a.「IT技術を活用した公共交通情報の収集、提供」とはどのようなものか。運営側、利用者側のそれぞれのメリットは。
b.「バス待ちスポット」「まち愛スポット」とは、どのようなものか。
c.「利用者目線でわかりやすい総合的な公共交通ガイドブックの作成」とあるがどのようなことを意識して作成するのか。
d.「市内病院の送迎バスの活用」「福祉分野の移動手段との連携」とは、どのようなものを想定しているか。
(4)狭山市地域公共交通計画(案)の計画目標3「効率的かつ利便性の高い公共交通ネットワークの構築」について
a.「まちづくりと連携した地域公共交通の形成」の具体的なイメージは。
b.狭山市の地域公共交通を一体的に協議する「分科会」は誰が、どのようにして協議を進めるのか。そこに市民の意見やニーズを反映させる仕組みはあるか。
c.「隣接市との広域連携に関する協議」は、どのように行われるのか。狭山市としてはそこで何を取り上げ協議する予定か。
―――質問と答弁の要旨―――
◆デマンドバスは実証運行終了後も継続
Q1 「ほりかねデマンドバス」実証運行の総括は。
A1 本事業は、地域主体でドア・ツー・ドアの移動サービスを提供し、地域住民の移動手段を確保、生活の質の向上に寄与するなど社会的意義は極めて大きい。このような社会的効果を勘案し、収支面での課題は依然として残るが、事業の継続を協議会に図り承認された。
◆分科会で狭山市の公共交通の一体的再編を協議
Q2 狭山市の地域公共交通を一体的に協議する「分科会」が設置される。誰が、どのように協議し、そこに市民ニーズを反映させる仕組みはあるか。
A2 路線バス事業者と検討した結果を踏まえ、専門的な知見を有するアドバイザーの協力のもと、地域公共交通活性化協議会の「住民、利用者」の代表者と協議を進める。公共交通の維持が難しい現状をご理解いただきつつ、地域に適した効率的な交通ネットワークの構築に向け、分科会で最善策を協議したい。
◆コミュニティバスの相互乗り入れを目指し隣接市と協議
Q3 「隣接市との広域連携に関する協議」は、どのように行われ、狭山市としては、何を取り上げ協議するのか。
A3 本市、所沢市、入間市、飯能市、日高市で構成される、いわゆるダイア5市の「公共交通部会」で、コミュニティバス等の相互乗り入れを取り上げ協議する予定。
◆利用者目線のガイドブックを作成
Q4 「利用者目線でわかりやすい総合的な公共交通ガイドブックの作成」との施策が示されているが、どのようなことを意識して作成するのか。
A4 公共交通ガイドブックの作成については、市内全体の交通機関を網羅し、シンプルで分かりやすいルート案内を提供することで、市民に「出かけたい」と思える内容にすることを意識したい。
◆公共交通を利用しやすい環境づくりを推進
Q5 快適にバスを待つことができる「バス待ちスポット」「まち愛スポット」とは、どのようなものか。
A5 バス利用者の利便性を高める取り組みのひとつで、登録されたバス停付近の公共施設や店舗をバスが来るまでの待機場所や、移動中の休憩やトイレの利用が可能なスポットとしてご利用いただけるもの。