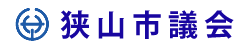
令和7年3月 定例会(第1回)
令和7年3月10日 (一般質問)
菅野淳 (創造)
録画を再生
1.小中学校の規模と配置の適正化
2.PTA活動
1.小中学校の規模と配置の適正化
(1)基本方針見直し
a.なぜ、小中学校の規模と配置の適正化が課題となったのか、その背景については。
b.その基本方針が平成19年に策定、平成30年にその改訂版が出され、そして6年後の令和5年に見直されたが、短期間のうちに見直しされたのはなぜか。
c.推計値と現況に乖離が生じたのは何故か、もう少し具体的に。
d.コーホート要因法とは。
e.平成30年にコーホート要因法を採用しなかったのは何故か。
f.今回の見直しのなかで、大きく変更された点は。
g.入間川東小学校の教室不足は予測できなかったことか。
h.児童・生徒が増加すると予想される学校があるが、教室数は大丈夫か。
i.入間川東小学校学区の中での市街化区域内の生産緑地の宅地変換、それに伴う人口増も予測不可能なことだったのか。
j.入間川東小学校の特別許可地区を令和4年に廃止したが、その緊急措置であったのか。
k.特別許可地区廃止の件は住民にしっかりと説明がなされたのか。
l.入間川東小学校に限らず、今後の進め方の1つとして地元検討組織を設置するとあるが、どの程度の規模(人数、期間、回数)で開催されるのか。
m.入間川東小学校は令和18年に教室不足が発生すると予測されているが、その対策としてどのような方法が考えられるか。
2.PTA活動
(1)家庭教育学級のリニューアル
a.家庭教育学級についてはどのように考えているか。
b.家庭教育学級開催後、参加者からどのような意見があったのか。
c.単位PTAにおける年間の家庭教育学級の平均開催回数は。
d.家庭教育学級の主な内容については。
e.来年度から家庭教育学級の方法がリニューアルされると聞いたが、具体的には。
―――質問と答弁の要旨―――
◆入間川東小学校の教室不足は予測不可能だった
Q1 「狭山市立小・中学校の規模と配置の適正化に関する基本方針」が、令和6年に見直しが図られ、そこで令和18年に入間川東小学校の教室不足が発生することが予測されたが、令和2年頃から関係者の中では教室不足の懸念が生じ始めていた。それは予測不可能だったのか。
A1 入間川東小学校区内の農地などで宅地開発が進行し、児童数増加が発生したため、社会増減による児童・生徒数の変化を加味していない将来推計では予測不可能であった。
◆特別許可地区の廃止
Q2 入間川東小学校の教室不足は、喫緊の課題であり、令和4年の特別許可地区の廃止は緊急措置であったのか。
A2 緊急措置として特別教室などを普通教室へ転用すると共に住民説明会を開催した後に特別許可地区の廃止を行った。
◆5つの対策案
Q3 入間川東小学校は令和18年に教室不足が発生すると予測されているが、その具体的な対策は。
A3 通学区の変更、仮設教室の建設、校舎の増築、現在の校地内での建て替え及び別の場所での建て替えなどだが、地元検討組織の意見を伺いながら決定していく。